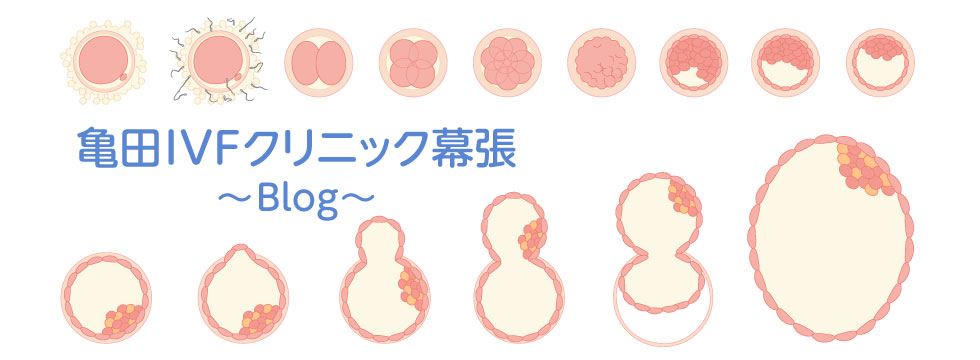生殖補助医療における腟内細菌叢と子宮内膜細菌叢の特性比較(Sci Rep. 2024)
【はじめに】
当院のブログは莫大な数のテーマを取り扱ってきているのですが、実は子宮内細菌叢をほとんど取り扱ってきませんでした。もちろん、理由をあって避けていたわけですが、①子宮内腔液・子宮内膜検体・腟内検体のどの検体が好ましいのか、②検査手法が確立(16S rRNAシーケンシングかqPCRか)されていないこと、③16S rRNAシーケンシングが共通であったとしても、シーケシングする部位によって結果が異なること、コピー数の補正をどのように考えるかなどです。ただ、患者様に先進医療で勧める以上、当院としてもスタッフ一同知識のアップデートを行い介入検討させていただく方向で動いています。不育症患者、反復着床不全患者を対象に考えています。
当院では、16S rRNAシーケンシングとqPCR両方を受けられるように準備しており、検体は内膜検体としております。子宮内膜細菌叢と腟内細菌叢の特性を記載した16S rRNAシーケンシングの論文をご紹介いたします。
【ポイント】
子宮内膜細菌叢は腟内細菌叢よりも多様性が高く、従来の分類法では一致しないため、子宮内膜細菌叢の評価が不妊治療予後の予測に重要な役割を果たす可能性があります。
【引用文献】
Alina Polifke, et al. Sci Rep. 2024 Dec 16;14(1):30508. doi: 10.1038/s41598-024-82466-9.
【論文内容】
着床不全や反復流産を持つIVF患者における腟内細菌叢と子宮内膜細菌叢を比較し、既存の腟内および子宮内膜細菌叢分類法の重複を調査することを目的としました。さらに、16S rRNAシーケンシングのV1-V2またはV2-V3領域の選択が生殖器細菌叢の特性評価にどの程度影響するかを明らかにすることも目的としていました。
研究方法としては、着床不全および/または反復流産と診断されたIVF患者から得られた腟スメアと子宮内膜生検サンプルのペア(n=71)間でV1-V2 rRNAシーケンシングに基づく細菌叢組成を比較しました。サブグループ(n=61)では、V1-V2とV2-V3 rRNAシーケンシング間の比較も実施しました。
結果:
腟内および子宮内膜細菌叢は患者の大多数でLactobacillus属が優勢であり、最も豊富なLactobacillus種は通常、同一患者の両サンプルタイプで共有されていました。子宮内膜細菌叢は腟内細菌叢よりも多様性が高く(平均Shannon entropy=1.89 vs. 0.75、p=10-5)、Corynebacterium sp.、Staphylococcus sp.、Prevotella sp.、Propionibacterium sp.などの細菌種が子宮内膜サンプルで増加していました。生殖器における細菌叢異常を検出するために広く使用されている2つの臨床分類法では、しばしば一致しない結果が得られました。細菌性腟症と関連するCST IVは患者の9.8%で検出されましたが、研究参加者の31.0%は不良な生殖転帰と関連するLactobacillus非優勢(NLD)子宮内膜細菌叢を有していました。V2-V3 rRNAシーケンシングに基づく結果はV1-V2ベースのものと概ね一致していましたが、Bifidobacterium sp.、Propionibacterium sp.、Staphylococcus sp.などの一部の種および CST IVとNLDの検出率がわずかに増加するなどの違いが認められました。
この研究は、経子宮頸管的サンプリング法を用いているにもかかわらず、子宮内膜細菌叢がその腟内対応物と実質的に異なることを示しています。子宮内膜細菌叢の特性評価は、IVF患者における不良な生殖転帰予後を持つ女性の検出改善に寄与する可能性があります。
【私見】
腟内細菌叢と子宮内膜細菌叢の比較において、子宮内膜細菌叢の方で有意に多様性が高いことが示されました。これは、先行研究であるRiganelli等の報告とも一致しています。そして、腟内細菌叢が正常であっても子宮内膜細菌叢に異常があるケースが多いことを示唆しています。
検査手法としては、16S rRNAのV1-V2領域とV2-V3領域という2つの異なる領域をターゲットにしてMiSeqシステム(Illumina社)でシーケンシングを行っています。
腟内細菌叢に対してはCST分類(Community State Type分類)が用いられています。
CST分類は、2011年にRavelらによって提唱された腟内細菌叢の分類システムです。この分類は16S rRNAシーケンシング技術を用いて腟内の細菌群集構造を分析し、優勢菌種に基づいて以下の5つの主要なタイプに分類します。優勢度が50%未満と定義されています。
CST I: Lactobacillus crispatus優勢
CST II: Lactobacillus gasseri優勢
CST III: Lactobacillus iners優勢
CST IV: Lactobacillus非優勢(嫌気性菌多種が優勢)
IV-A: Gardnerella vaginalisが増加
IV-B: G. vaginalisとAtopobium vaginaeが増加
IV-C: 多様な嫌気性菌が増加
CST V: Lactobacillus jensenii優勢
子宮内膜細菌叢に対するLD/NLD(Lactobacillus優勢/非優勢)分類スキーム(Lactobacillus abundanceが90%未満)が用いられています。
#腟内フローラ(細菌叢)
#子宮内フローラ(細菌叢)
#Lactobacillus
#細菌性腟症
#亀田IVFクリニック幕張
文責:川井清考(院長)
お子さんを望んで妊活をされているご夫婦のためのブログです。妊娠・タイミング法・人工授精・体外受精・顕微授精などに関して、当院の成績と論文を参考に掲載しています。内容が難しい部分もありますが、どうぞご容赦ください。
当ブログ内のテキスト、画像、グラフなどの無断転載・無断使用はご遠慮ください。