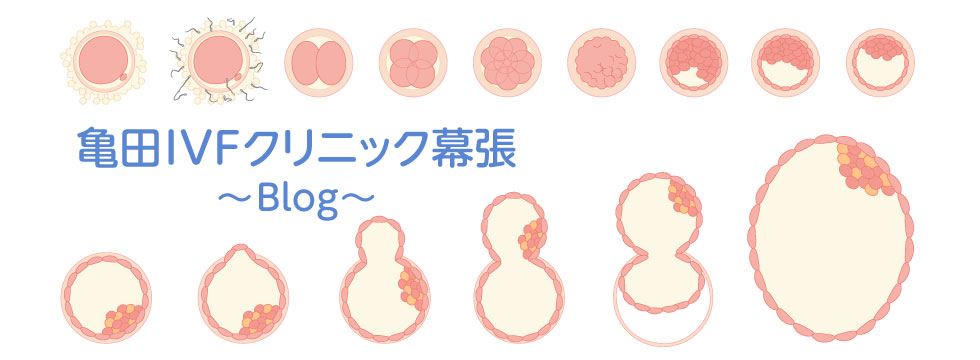RhD陰性妊婦の妊娠初期流産・中絶に対する取り扱い(Am J Obstet Gynecol. 2024)
RhD陰性妊婦の妊娠初期流産・中絶に対する取り扱いはCQ008-1 に記載されています。産婦人科診療ガイドライン産科編2023では、「自然流産・人工妊娠中絶・異所性妊娠後・胞状奇胎手術後、双胎一児死亡、妊娠中の羊水穿刺、絨毛採取、胎位外回転術などの処置後、腹部打撲後などの妊娠女性に関して抗D免疫グロブリンを投与する」(推奨度B)となっています。
≪ポイント≫
母体胎児医学協会(SMFM)が同様のstatementを出しました。より強く推奨できる環境になったのかなと思っています。
≪論文紹介≫
Practice Guideline Am J Obstet Gynecol. 2024 May;230(5):B2-B5. doi: 10.1016/j.ajog.2024.02.288.
妊娠初期流産および人工中絶管理に関するガイドラインは、RhD検査および抗D免疫グロブリン投与の観点で様々です。妊娠12週未満の流産または人工妊娠中絶による抗RhD抗体の発症率は低いものの、大きい母集団で考えると無視できない範疇だと考えられています。抗RhD抗体の影響は、その後の妊娠のたびに増大し、胎児・新生児の貧血と早期黄疸で、重症の場合は胎児水腫、死産と関連します。RhD抗原に感作された後の妊娠による有害転帰を考慮すると、その後の妊娠の可能性があるRhD陰性女性では、感作を防ぐことが重要です。管理上および財政的に実行可能であり、中絶ケアへのアクセスを妨げない医療環境においては、RhD抗原に感作されていない女性に対して、妊娠12週未満の妊娠初期流産および人工中絶の両方に対してRhD検査と抗D免疫グロブリン投与を行うことを推奨します。
抗D免疫グロブリン投与が必要な場合、自然流産または人工妊娠中絶後72時間以内に50μgを投与すれば十分にカバーできると推奨しています。低用量の入手が困難な臨床現場もあるため、低用量が利用できない場合は300μgの抗D免疫グロブリン投与を推奨します。
≪私見≫
日本人ではRhD陰性の頻度が約0.5%と低く、なかなか遭遇しないケースですので丁寧に説明する必要がありますね。
妊娠中期に投与することで、分娩前のRhD抗原への感作リスクが1.8%から0.1~0.2%に減少します。RhD陰性の患者では、抗D免疫グロブリンを分娩後に投与することで、分娩後のRhD抗原への感作リスクが13~17%から1~2%に減少します。RhD抗原は赤血球のみに発現するため在胎週数6週以降には感作の可能性がでてきます。
今回のSMFMの声明でも、産科ガイドライン2023でも出血を繰り返す切迫流産や分娩前異常出血の抗D免疫グロブリンは、ほぼ記載されていません。
#RhD陰性妊婦
#妊娠初期流産・中絶
#抗D免疫グロブリン
#SMFM statement
#亀田IVFクリニック幕張
文責:川井清考(院長)
お子さんを望んで妊活をされているご夫婦のためのブログです。妊娠・タイミング法・人工授精・体外受精・顕微授精などに関して、当院の成績と論文を参考に掲載しています。内容が難しい部分もありますが、どうぞご容赦ください。
当ブログ内のテキスト、画像、グラフなどの無断転載・無断使用はご遠慮ください。