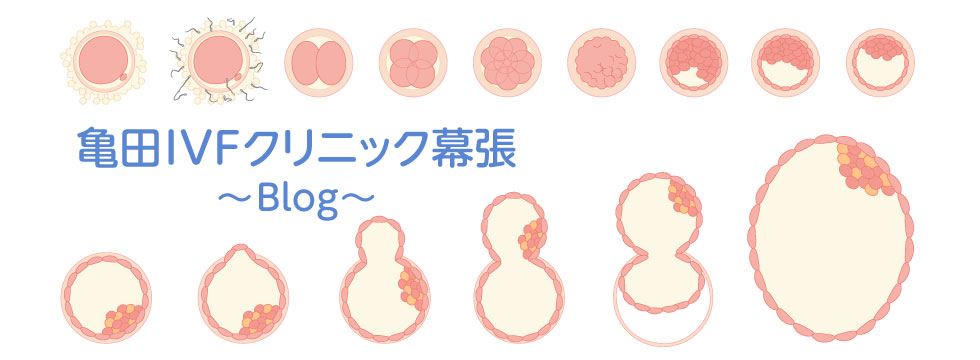朝食摂取が体外受精の治療成績に与える影響(Nutrition. 2024)
【はじめに】
生活習慣と不妊治療の成績との関連が注目されています。特に食事のタイミングと生殖機能の関係については、時計遺伝子との関連が示唆されています。朝食欠食は、肥満、メタボリックシンドローム、2型糖尿病、脳卒中、冠状動脈疾患などのリスク増加と関連することが知られていますが、不妊治療における影響についてはよくわかっていません。今回、朝食摂取と体外受精治療成績との関連について調査した研究をご紹介いたします。
【ポイント】
週6-7回の朝食摂取習慣がある患者さんでは、体外受精による出生率が高く、流産率が低いことが示されました。
【引用文献】
Masanori Ono, et al. Nutrition. 2024 Nov:127:112555. doi: 10.1016/j.nut.2024.112555.
【論文内容】
不妊治療を受ける女性患者における食事摂取頻度とART治療成績との関連を評価することを目的としたコホート研究です。
2022年2月から2024年1月まで、脳卒中、心臓病、がん、1型または2型糖尿病の既往がない不妊症女性117名に質問票を配布し、101名から回答を得られた患者を対象としました。質問票から、ART治療前と20歳時の食事摂取頻度、喫煙状況、飲酒状況などの情報を収集し、年齢、BMI、AMH値、出産歴などのデータは診療記録から収集しました。
朝食摂取については、週6-7回を習慣的な朝食摂取群、週0-5回を非習慣的摂取群と定義しました。同様に、昼食と夕食についても週の摂取頻度で分類しました。生殖医療結果としては、臨床的妊娠、妊娠継続率、出生率、流産率を評価しました。
結果:
101名患者のうち、週6-7回朝食を摂取する群は53名、週0-5回群は48名でした。多変量解析において、週6-7回朝食摂取群は有意に高い生産率(オッズ比 3.030、95%信頼区間 1.048-8.771)と低い流産率を示しました。昼食(週6-7回:87名、週0-5回:14名)および夕食(週6-7回:93名、週0-5回:8名)の摂取頻度については、治療成績との有意な関連は認められませんでした。
【私見】
朝食を定期的に摂取することがよさそうですね。Clock gene発現異常、代謝異常、生殖ホルモン異常などが関連するのかもしれません。色々なバイアスが影響する可能性がありますが、健康的な生活習慣を行うように心がけるところからはじめていくのがよいかもしれませんね。
#朝食摂取
#体外受精
#生活習慣
#時計遺伝子
#亀田IVFクリニック幕張
文責:川井清考(院長)
お子さんを望んで妊活をされているご夫婦のためのブログです。妊娠・タイミング法・人工授精・体外受精・顕微授精などに関して、当院の成績と論文を参考に掲載しています。内容が難しい部分もありますが、どうぞご容赦ください。
当ブログ内のテキスト、画像、グラフなどの無断転載・無断使用はご遠慮ください。